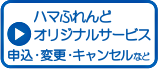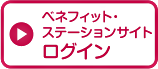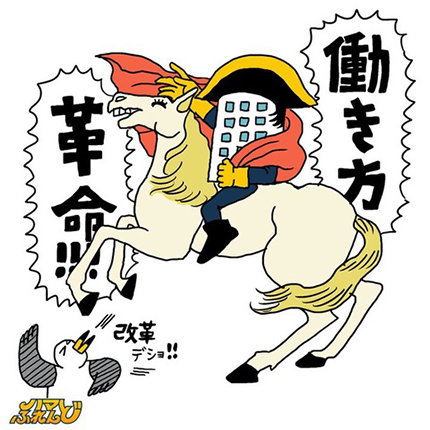注)当コラムに掲載された情報の正確性・完全性については最善を尽くしておりますがその内容を横浜市、事業受託者株式会社ベネフィット・ワンおよび執筆者が保証するものではありません。
また、当コラム内容は、横浜市および事業受託者株式会社ベネフィット・ワンの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。
過度の残業や長時間労働によるうつ病や自殺などが大きな社会問題となっている昨今。
社員の体調管理はもはや社員本人だけの問題ではなく、社員が心身ともに健康に働けるように健康管理にも配慮することは会社の重要な義務の一つとなっています。
今回は企業に求められる社員の健康管理義務について。
社員の健康管理をする重要性や意義、企業でできる取り組みの具体例などについてご説明します。
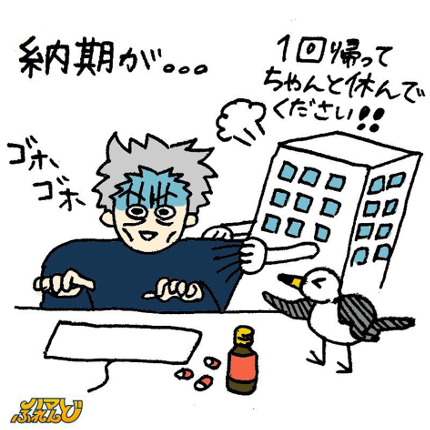
社員の健康管理は法律上の義務!「安全配慮義務」とは?
2008年に施行された労働契約法で、「企業は従業員に対して生命や身体の安全を確保しながら働けるように配慮する義務がある」ということが明文化されました。
上記のように、使用者が雇用者に対して生命や身体の危険から保護するための環境を用意しなくてはいけないことを「安全配慮義務」といいます。
それまでも判例上では、使用者は雇用者に対する「安全配慮義務」があるとされていましたが、法律上の明確な根拠はありませんでした。
これを、当然に必要な義務として明文化したのが2008年施行の労働契約法です。
労働契約法自体に罰則規定はありません。
しかし、労働契約法施行以前から今日にいたるまで、安全配慮義務を怠ったことによるトラブルや訴訟について、企業への損害賠償を命じる判決が多数存在しています。
また、労働安全衛生法では生命や身体の保護だけでなく、社員にとって快適な職場環境作りを積極的に行うことも求められています。
では、社員の健康を守るために具体的にどのような配慮をしたらいいのでしょうか?
安全配慮義務を守るためにおさえておきたいポイントは次の4つです。
適正労働条件措置義務
過重労働が原因となって心身の健康を害さないために、労働時間や休憩・休日、休憩場所、人員配置などの労働条件を適正に保つ義務です。
昨今、過重労働による過労死や過労自殺が社会問題となっているように、適正な労働時間を管理することは企業にとって最も配慮すべきことの一つといえます。
従業員自身が過重労働に対して問題ないと考えている場合でも、企業側で適切な労働時間を管理する必要があります。
健康管理義務
必要に応じて健康診断やメンタルヘルス対策を行い、労働者の心身の健康状態の把握と健康管理に努める義務です。
労働安全衛生法では、健康診断の実施についてタイミングなどが詳しく定められています。
雇い入れたときや、1年に1回定期的に健康診断を行い、深夜業や身体に有害な物の取り扱いや有害な環境での従事者には特定業務従事者健診を行うことが義務付けられます。
ただ単に健康診断を実施するだけではなく、健康診断の結果が出た後についても、企業は従業員に対して適切な処置をとる必要があります。
適正労働義務
労働者の病歴、持病、体調などを考慮した業務配置を行う義務です。
従業員が業務によって心身の不調を訴えた場合や持病がある場合などに、企業がそれに対する対応を怠った場合には、安全配慮義務違反になることがあります。
適切な業務配分を行うほか、現在健康な従業員でも急な身体不良を起こす可能性もあるため、もしもの際に適切な対応ができるような体制を整えておくことも重要です。
看護・治療義務
病気やケガをした場合に適切な看護や治療を行う義務です。
従業員が業務によってケガをしたり精神障害を発症したりした場合に、企業が適切な看護や治療を行うのはもちろんですが、「発症した可能性」がある場合にも対応する必要があります。
日頃から従業員とコミュニケーションを取り、少しでも異変があった場合には病院で受診をしてもらいましょう。
社員の健康管理をする意義とは?健康経営の考え方も確認
社員の健康管理は、生産性や顧客満足度を上げ、経営リスクやコスト発生の可能性を抑えるためにも重要です。
近年、社員の健康管理が企業の経営にも大きな成果をもたらすという「健康経営」の考え方が広く取り入れられています。
健康経営とは1980年代にアメリカで生まれた考え方のことで、従業員の健康管理を経営的な視点・戦略として実践するものです。
社員の健康や体調の管理を行うことによってもたらされるメリットについて、具体的に見ていきましょう。
健康管理の意義① 生産性や顧客満足度の向上
会社において社員がイキイキと活躍するためには、健康であることが大前提です。
社員が健康であるからこそ高品質の商品やサービスを提供することができ、それが顧客満足度の向上や、ひいては会社の業績アップなど成長にもつながります。
体調不良や疲労が蓄積した状態で業務を行うとミスや事故など重大なトラブルを引き起こしてしまう可能性もあり、経営リスクにもつながりかねません。
健康管理の意義② 休職者や離職者の減少
健康管理を適切に行っている会社では、病気やメンタルの不調による休職者や離職者が減少するというメリットも見込めます。
休職者や離職者が増えると企業の活動に必要な人材を確保することが難しく、一定の質で商品やサービスを提供することも困難になるでしょう。
病気やメンタルの不調が原因で社員が退職してしまった場合、その後の採用や教育といったコストも発生してしまいます。
健康管理の意義③企業のイメージアップ
社員が健康にイキイキと働けていることは、外部からのイメージアップにもつながります。
企業のアピールポイントになり、企業のブランディングや一般消費者へのアピールにも効果的です。
企業イメージがよくなることで、売上増加や優秀な人材の確保が期待できます。
社員の健康管理のためにできる具体的な取り組み
すでに多くの会社で社員の健康管理をするためのさまざまな取り組みが進められています。
具体的な取り組みの事例について、5つ見ていきましょう。
健康管理の取り組み① 長時間労働を改善する
過度な残業や長時間労働は、メンタルにも体にも悪影響を及ぼします。
社員の勤怠を管理して、特定の部署だけ長時間労働をしている社員が多くなっていないか、特定の社員だけ残業が多くなっていないかなどをチェックしましょう。
2020年4月より、中小企業にも時間外労働の上限規制が法律によって適用されています。
時間外労働の上限は原則として、月45時間、年360時間までで、違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
とはいえ、仕事の量が減らないのに労働時間が減ってしまい、時間が足りないということもあるでしょう。
まずは、無駄な作業がないか、効率化できる作業や外注できる作業がないかなど、労働環境の見直しを。
見直しをしてもなお労働時間の確保が難しいということであれば、人員を増員するなどマンパワーの充実を図るなどの対応が必要でしょう。
健康管理の取り組み② 健康診断を行う
働きながら健康を維持するのは案外難しいもの。
健康診断は「安全配慮義務」の健康管理義務にある通り、すべての従業員が受けなければならないものです。
医師による健康診断によって重大な疾患や病気を早期発見できることもあり、症状が発生する前に病気のリスクを予防したり、医療費を軽減したりすることにもつながります。
健康診断は、1年以上雇用する予定で週の労働時間が正社員の4分の3以上である従業員に実施義務があり、条件を満たすパートやアルバイトも対象となります。
健康管理の取り組み③ 職場環境を整える
社員が健康的に働けるような職場環境を整えることも大切です。
オフィスの室温や湿度、日当たり、風通しなどを改善させるのはもちろん、社員1人1人の作業スペースを十分確保し、休憩できるスペースを用意することも必要となります。
さらに、レクリエーション企画で体を動かす機会を作ったり、社員食堂で栄養バランスのいい食事を提供したりすることも効果的でしょう。
健康セミナーなどを行い啓発活動を実施するのも、良い取り組みです。
全体で活動するのが難しいという場合は、毎日運動をするなどの健康管理を行った従業員に、図書カードやクオカードなどの粗品を進呈するなどの取り組みも良いでしょう。
健康管理の取り組み④ ストレスチェックやカウンセリングの実施
体の健康を管理することはもちろん、今日の日本ではメンタルヘルスに対しても大きな関心が寄せられています。
2015年12月より、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回のストレスチェックが義務付けられました。
ストレスチェックでは、ストレスに関する質問票に労働者が回答することで自分自身のストレス状態に気づき、セルフケアのきっかけを作ります。
労働者が50人未満の事業所でも努力義務となっているため、定期的にストレスチェックを実施することが望ましいでしょう。
またそれ以外にも、産業医を配置してカウンセリングや、相談窓口を設置することも重要です。
企業におけるメンタルヘルス対策の重要性や具体的な対策方法については「企業のメンタルヘルス対策を解説!不調の原因から具体的な進め方まで」も併せてご覧ください。
健康管理の取り組み⑤ 福利厚生を充実させる
上記で紹介した取り組みの中には、福利厚生として取り入れられるものもあります。
例えば、健康診断やスポーツジムの利用、メンタル相談窓口などの設置は福利厚生の一環として取り入れている企業も多いです。
福利厚生のアウトソーシングにより比較的取り入れやすい取り組みでもあります。
福利厚生の充実は体調管理だけではなく、社員の満足度にもつながります。
社員の健康管理で何をして良いか困った場合には、福利厚生のアウトソーシングサービスの利用も検討してみると良いかもしれませんね。
福利厚生アウトソーシングについては過去のコラムも併せてご覧ください。
「福利厚生をアウトソーシングするメリットを知って経営に活かす!」
社員の健康管理・体調管理のための取り組みを実施しよう
社員の健康管理は、もはや会社の経営に関わる重要な課題となっています。
2008年に施行された労働契約法では、使用者の雇用者に対する「安全配慮義務」も改めて明文化されました。
安全配慮義務には、適正労働条件措置義務、健康管理義務、適正労働義務、看護・治療義務があります。
労働者の心身の健康を維持することは、企業が生産性や顧客満足度を向上させ、休職者や離職者を減らし、企業のイメージアップを図るためにも必要不可欠です。
長時間労働を改善し、健康診断を行い、職場環境を整え、ストレスチェックやカウンセリングを実施するなど、具体的な取り組みを実施しましょう。
これらの取り組みは福利厚生によってアウトソーシングできることもあります。
社員の健康に対する義務や取り組みなどを知って、社員一人ひとりを大切にした経営を目指していきましょう。